葬儀の基礎知識
【苫小牧市で考える】家族が「余命1ヶ月」と言われたときにできること
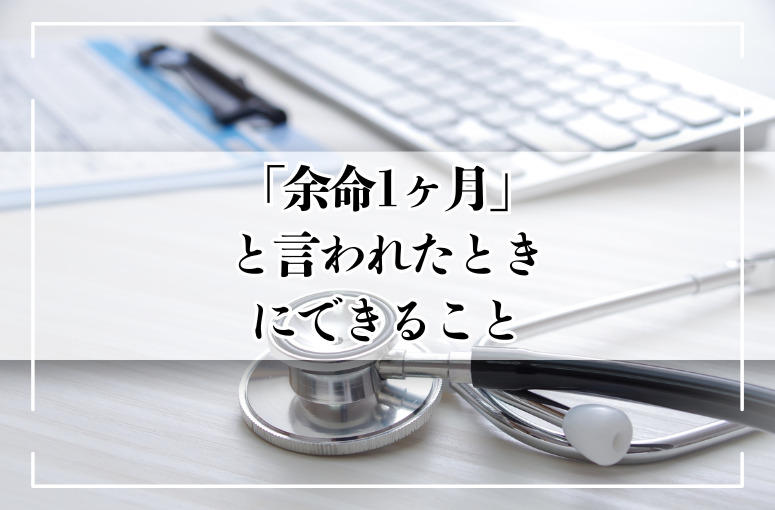
公開日: 2025年10月28日 11:00
最終更新日: 2025年10月29日 09:30
もしも大切な家族が医師から「余命1ヶ月」と告げられたら――。多くの方は深い悲しみと混乱に包まれ、何をどうすれば良いのか分からなくなるでしょう。しかし、時間は止まりません。限られた日々をどう過ごすかを考えることが、ご本人と家族の心の整理につながります。
この記事では、余命宣告を受けたあとの心構えや過ごし方、そしてご家族ができる準備について、苫小牧市でのサポート環境にも触れながら解説します。
目次
余命宣告は「必ずそうなる」とは限らない
余命宣告は、医師が現在の病状や治療経過をもとに「あとどのくらい生きられるか」を伝えるものです。しかし、これはあくまで“予測”であり、100%その通りになるわけではありません。苫小牧市でも、医師の見立てよりも長く穏やかに過ごされた方の例は少なくありません。
とはいえ、「限られた時間」が現実であることも事実です。ご本人とご家族が後悔しないためにも、残された日々を大切にしながら、できる準備を少しずつ進めていきましょう。
まずは心を落ち着かせることから始めよう
余命宣告を受けた直後は、誰もが強い動揺を覚えます。今後の生活や治療を考えなければいけないと分かっていても、気持ちが追いつかないこともあるでしょう。
そんなときは、まず「心を落ち着かせる」ことを意識してください。過去の後悔や不安に囚われるよりも、「残された時間をどう生きるか」に焦点を当てることが大切です。苫小牧市内には、心のケアをサポートしてくれるカウンセラーや医療相談窓口もあります。孤独を感じるときは、専門家の力を借りるのも一つの方法です。
家族がしてあげられる5つのこと

余命宣告を受けたあと、家族としてできることを整理しておきましょう。
① 病気について正しく理解する
まずは、医師から病状や治療方針についてしっかり説明を受け、正しく理解することが大切です。聞き逃した点や分からない点は遠慮せず質問しましょう。ご本人と家族が病気を理解することで、より良い支え方を考えられるようになります。
② ご本人の気持ちに寄り添う
一番つらいのは、ご本人です。怒りや悲しみを家族にぶつけてしまうこともあるかもしれませんが、それも自然な感情です。苫小牧市でも、在宅医療や緩和ケアチームが心のサポートを行っている医療機関があります。家族が現実を受け入れ、前向きな姿勢を見せることで、ご本人も安心できます。
③ そばに付き添い、孤独にさせない
強く見える方でも、内心は不安でいっぱいです。できるだけ一人にせず、穏やかな時間を共有しましょう。付き添うことで、体調変化にもすぐ気づくことができます。特に在宅療養の場合、近隣の訪問看護ステーション(苫小牧市内にも多数あります)を利用することで、ご家族の負担を減らすこともできます。
④ 前向きな言葉をかける
落ち込んでいるご本人に対して、「頑張ってね」「かわいそう」などの言葉は避けた方がよいといわれています。それよりも「今日も会えてうれしいね」「一緒にご飯を食べよう」など、自然で温かい言葉をかけてあげましょう。無理に励ますよりも、安心できる空気を作ることが何よりの支えになります。
⑤ やりたいことを一緒に考える
行きたい場所、食べたいもの、会いたい人――。ご本人の「やりたいこと」を聞いてあげましょう。苫小牧市には自然豊かな場所や港町ならではの景観スポットも多く、短時間でも気分転換できる場所があります。体調を見ながら、小さな「願いの実現」をサポートしていきましょう。
家族が進めておきたい現実的な準備

心のケアと同時に、実務的な準備も少しずつ進めておくと安心です。
治療方針を相談する
積極的治療・延命治療・緩和ケアの3つの選択肢の中から、ご本人の希望を中心に話し合いましょう。苫小牧市内の病院では、在宅緩和ケアや訪問診療を行う医療機関もあります。地域の医療連携を活用しながら、最適な方法を選びましょう。
エンディングノートの作成
ご本人の思いや希望をまとめるエンディングノートを準備することで、家族の心の負担を軽減できます。書くことでご本人自身の気持ちも整理され、心の準備を進めることができます。
相続や遺言の確認
財産や保険、借入などの状況を家族で共有し、必要であれば弁護士や税理士に相談して遺言書を作成しましょう。事前に話し合っておくことで、後々のトラブルを防げます。
葬儀の準備も早めに
「まだ早い」と感じるかもしれませんが、事前に葬儀の流れや費用を知っておくことは大切です。苫小牧市内には家族葬や小規模葬に対応した葬儀社も多く、事前相談を無料で行っているところもあります。あらかじめ話を聞いておくことで、いざという時に慌てずにすみます。
後悔のないお別れのために、心の準備と現実的な準備を少しずつ進めていきましょう。
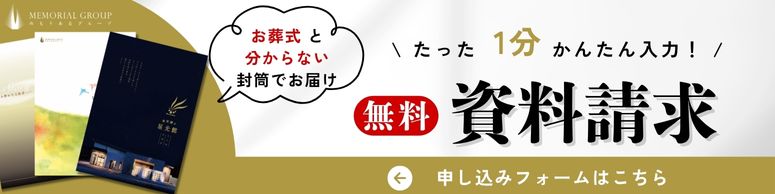




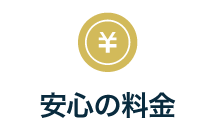
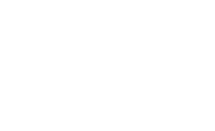
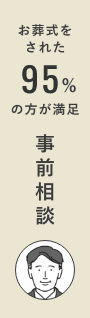


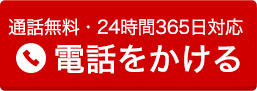
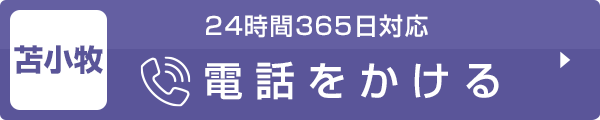
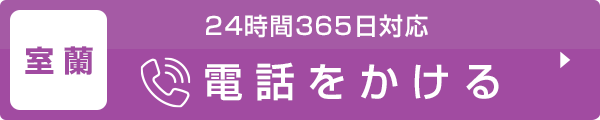
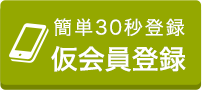
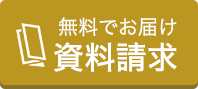

クチコミ件数
1,524件平均評価
4.9