葬儀の基礎知識
初七日(しょなのか)の数え方
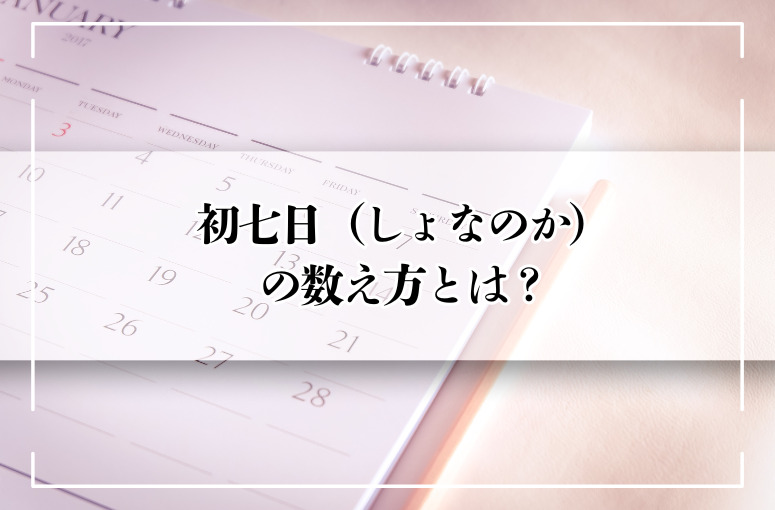
仏教では、故人が亡くなってから7日目に「初七日(しょなのか)」と呼ばれる1回目の追善法要を行います。「聞きなじみはあるものの、初七日の数え方がよくわからない」という方のために、この記事では初七日の数え方や初七日の意味、法要の種類についても解説します。
目次
法要の種類について
仏教では、初七日をはじめとしたさまざまな法要が執り行われます。まずはその種類を紹介します。
忌日法要(きじつほうよう)
● 初七日(しょなのか/しょなぬか):7日目
● 二七日(ふたなのか/ふたなぬか):14日目
● 三七日(みなのか/みなぬか):21日目
● 四七日(よなのか/よなぬか):28日目
● 五七日(いつなのか/いつなぬか):35日目
● 六七日(むなのか/むなぬか):42日目
● 七七日(なななのか/なななぬか)もしくは四十九日(しじゅうくにち):49日目
● 百箇日(ひゃっかにち):100日目
年忌法要(ねんきほうよう)
● 一周忌 (いっしゅうき):満1年目
● 三回忌 (さんかいき):満2年目
● 七回忌(ななかいき):満6年目
● 十三回忌(じゅうさんかいき):満12年目
● 十七回忌(じゅうななかいき):満16年目
● 二十三回忌(にじゅうさんかいき):満22年目
● 二十七回忌(にじゅうななかいき):満26年目
● 三十三回忌(さんじゅうさんかいき):満32年目
一般的には、三十三回忌をもって弔い上げ(年忌法要を終了)とすることが増えています。その理由としては、多くの宗派(※宗派によって異なる場合があります)では、33年経つとすべての霊魂が等しく極楽浄土へ行けるとされていること、遺族が高齢となり法要を行うことが困難になること、故人を知る人が減ることが挙げられます。
忌日法要について

仏教では、人が亡くなると霊魂は現世を離れて中陰(ちゅういん)へ入るとされています。中陰は中有とも呼ばれ、来世の行き先を決める裁判が行われるまでの期間のことを指します。
中陰は49日間続きますが、その間の「霊魂は行き先が決まらず、あの世とこの世をさまよっている状態となります。これが俗に言う「冥土(めいど)の旅」という状態です。そして、霊魂は死後7日ごとに生前の行いを裁かれ、49日目に仏様のいる極楽浄土へ向かいます。
仏教の考えにおいては小さな嘘をつくことや虫を殺すことなども罪とされますが、たとえ故人が生前に罪を犯していたとしても、遺族が供養をすることで故人の善を積むことができます。つまり、故人の霊魂がより良い世界に生まれ変わるために祈る行為が「忌日法要」なのです。
初七日法要について

忌日法要のなかでも「初七日」は、霊魂が三途の川のほとりに到着する大事な節目の日です。霊魂は生前の行いに対しての裁きを受け、三途の川の流れがおだやかな場所を渡るか、流れが激しい危険な場所を渡るかが決められます。
そのため残された遺族は、故人の霊魂がおだやかな流れの場所を渡れるよう手を合わせ祈るのです。その後も、遺族は7日ごとの裁きの日に合わせて法要を行い、故人の霊魂が裁きを受けて無事に成仏ができるよう祈ります。
初七日の数え方
従来、初七日の数え方は「亡くなった日を含んだ7日目」です。たとえば、亡くなった日が月曜日だとすると、初七日は翌週の月曜日ではなく日曜日になります。葬儀の日や火葬をした日と勘違いしている方も多いので注意しましょう。そのため、葬儀を行うタイミングによっては、葬儀当日にはすでに初七日を過ぎてしまっているケースもあります。
ところが、近年では火葬場がひっ迫している等の事情により、初七日を繰り上げたり繰り込んだりすることも増えてきています。これを「繰り上げ初七日法要」、もしくは「繰り込み初七日法要」と呼び、現在はこちらの方法が一般化しています。
初七日法要の準備の流れ
初七日法要を行う場合、7日間ですべて準備をしなければならないため速やかに準備をすることが重要です。初七日法要の準備の流れについては以下の通りです。
1. 初七日の日取りと場所を菩提寺と相談して決める
2. 初七日法要に招く方に声をかける
3. 返礼品を用意する
4. 会食(精進落とし)のお膳やお弁当の手配をする
5. 自宅で行う場合は、後飾り祭壇(中陰壇)に位牌や遺骨、遺影を配置する
※後飾り祭壇は葬儀屋で準備する2段~3段の祭壇のことです。また、四十九日までは中陰壇とも呼びます。
※祭壇は机に白布をかけたもので代用しても問題ありません。
※お寺で行う場合は、位牌、遺骨、遺影写真を持参しましょう。
初七日法要の式の流れ
初七日法要の式の流れは以下の順番になります。
1. 参列者の着席・住職入場
2. 開始の挨拶
3. 住職による読経
4. 遺族・親族による焼香
5. 住職の法話
6. 喪主による挨拶
7. 閉式(ここまでで30分程度)
8. 会食(精進落とし)
9. 挨拶と返礼品の配布
10. 解散
初七日法要の場合は参列者が着席後すぐに始めるケースが多いため、お寺へのお布施を渡すタイミングを逃してしまうこともあるかもしれません。その場合は、閉式後のお渡しになっても失礼ではありませんので忘れずに渡しましょう。
また、初七日法要は、自宅ではなくお寺や葬儀会館などを使用する場合もあります。法要の場所については事前に家族や住職と相談して目処をつけておきましょう。
繰り上げ初七日法要とは
「繰り上げ初七日法要」とは、葬儀と火葬の後に葬儀場やお寺に移動して初七日法要を行う流れのことを指します。
僧侶が遺骨に対して読経を行う本来の初七日法要と同じ形式ではあるものの、繰り上げ初七日法要の場合は、その後に法要会場に移動したり会食(精進落とし)をしたりするため拘束時間が長くなり負担がかかりがちです。
繰り込み初七日法要とは
「繰り込み初七日法要」とは、葬儀や告別式を行った後にそのまま続けて初七日法要を行う流れのことを指します。
繰り込み初七日法要は、火葬場に向かう前に初七日法要まで終わらせるため、火葬場に同行しない親戚とも一緒に供養が可能です。また、移動による負担や拘束時間が少なく効率的というメリットもあるため、現在では繰り込み初七日法要を希望する人が増えています。
とはいえ、遺骨に対して読経をする本来の流れに対して、繰り込み初七日法要の場合は遺骨になる前に法要を行ってしまうため、寺院や地域によってはまだ繰り込み初七日法要を認めていないところもあります。繰り込み初七日法要を検討している場合は事前にしっかりと確認することが重要です。
初七日法要の服装

初七日法要は、葬儀と同じように喪服の着用が一般的です。「アクセサリーは真珠のものや結婚指輪のみにし、殺生を連想させる毛皮やファーは使用を控えます。
家族だけで行う初七日法要は平服でよい場合もありますが、平服は普段着とは異なるためカジュアルにならないように注意しましょう。
● 男性の平服例:ダーク系のスーツ・白いワイシャツ・黒のネクタイ・黒い靴・黒い靴下
● 女性の平服例:ダーク系のワンピース・スーツ・アンサンブル・ネックレス・イヤリングは真珠・黒いカバン・黒い靴・黒いストッキング
● 子どもの平服例:制服・制服がない場合は白いシャツ・ダーク系のズボンやスカート・黒い靴下




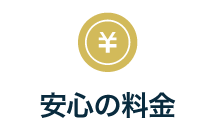
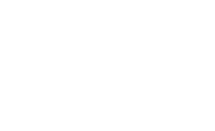
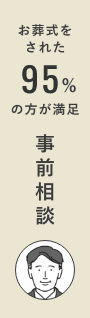


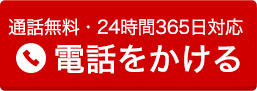
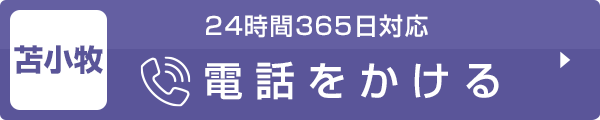
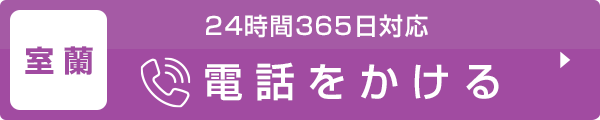
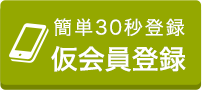
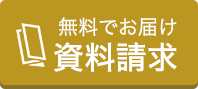
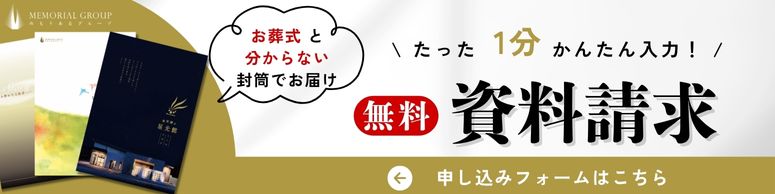

クチコミ件数
1,524件平均評価
4.9