葬儀の基礎知識
家族が「余命1ヶ月」と言われたとき—残された時間にできること|室蘭市での準備と心構え
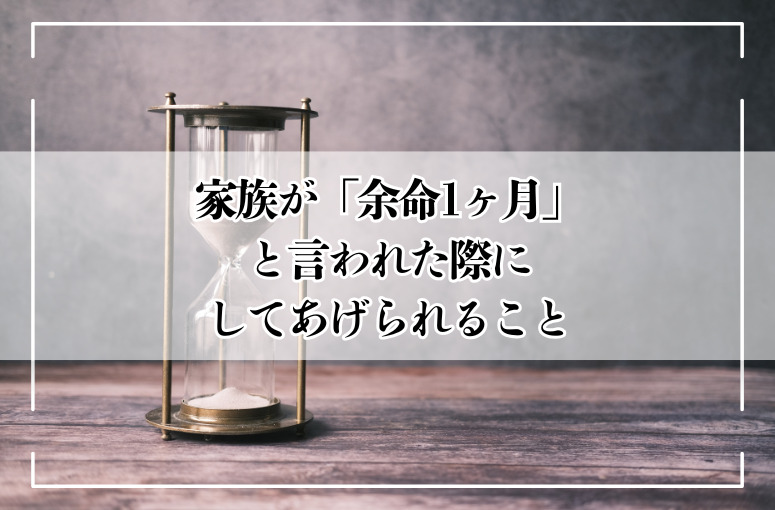
大切な家族が「余命1ヶ月」と告げられたとき、多くの方は深い悲しみと混乱で、何から手を付ければよいか分からなくなります。けれども、時間は止まりません。今できることを一つずつ整えることで、ご本人と家族の心は少しずつ落ち着き、限られた日々をより穏やかに過ごせるようになります。
本記事では、余命宣告後の心構え、過ごし方、家族が進めたい準備を分かりやすくまとめました。地域の慣習や支援体制には差があるため、室蘭市での手続き・相談先を意識した視点も交えてご紹介します。
目次
余命宣告は「予測」—100%その通りとは限らない
余命宣告は、医師が病状・経過を踏まえて示す医学的な見立てであり、確定ではありません。実際には想定より長く過ごせる方もいれば、短くなる場合もあります。いずれにしても、「残された時間をどう生きるか」に焦点を当て、ご本人と家族が納得できる選択を重ねていくことが大切です。
【最初の一歩】心を整える
大事な家族が余命宣告を受けると、多くの人は激しく動揺し混乱することでしょう。今後のことを考えていかなければならないのに、落ち着いて考える余裕はないと思います。しかし、これから待ち受ける現実に向けて、しっかりと動き出さなければいけません。
そのためには、まずは心を落ち着かせることを目指しましょう。つい過去を後悔したり嘆いたりしたくなるかもしれませんが、大事なことは、残された時間をどれだけご本人と寄り添い生きていくのかということです。
現実を悲観するのではなく、ご本人と家族にとってこれからの毎日が幸せな日々となるよう、前向きに生きるための方法を考えましょう。
【余命宣告を受けたら】してあげられることを考える
余命宣告を受けたら家族としてなにができるのでしょうか。ここでは、家族がしてあげられることについてご紹介します。
病気について正しく理解する
まずは、ご本人はもちろん、家族も一緒になって、病気についての正しい理解や知識を持つことが重要です。医師から聞いた説明をしっかりと理解し、今後の治療方針や病気の進行について話し合っていきましょう。
もし、その際に不明点があれば、積極的に医師に質問してみてください。ご本人と家族、双方が病気について理解することでコミュニケーションが取りやすくなるため、ご本人の病状に合った適切なサポートができるようになります。
ご本人の気持ちに寄り添う
当たり前のことですが、余命宣告を受けて一番つらいのはご本人です。家族に感情をぶつけたくなることもあるでしょう。しかし、どれだけ傷つこうとショックを受けようと、家族はご本人の気持ちに寄り添いましょう。
余命宣告はご本人だけではなく家族にとってもつらい現実であるため、受け入れることがなかなか難しいことではありますが、家族が現実を受け入れ前向きな気持ちになることはご本人にとって大きな支えになるはずです。いつかその日が来ても後悔なく送り出せるようご本人に寄り添い、残された大事な日々を一緒に楽しむことが重要です。
そばに付き添う
なかには、余命宣告を受けたあとも気丈にふるまう方がいらっしゃいます。しかし、内心は不安でいっぱいになっているはずなので、なるべく一人にさせず付き添いましょう。
人生最大の試練が訪れたときに自分一人で立ち直れる方は、そんなに多くはありません。絶望したくなるほどの恐怖を抱えている状態のときほど、身近に誰かがいることで気がまぎれたり不安が軽減されたりするものです。
またそばにいることで、非常事態が起きた際に医師にすぐに連絡ができたり適切に対応できたりします。家族はなるべくそばで見守ってあげましょう。
前向きな言葉をかける
きっと、ご本人は誰よりもネガティブな気持ちになっているはず。それに加えて、家族までもがネガティブになってしまうとお互いにつらくなるだけです。家族は悲しい気持ちをぐっとこらえて、励ましの言葉や前向きになる言葉をかけてあげましょう。そうすることでご本人だけではなく、家族もきっとポジティブな気持ちになっていくはずです。
とはいえ、以下の言葉をかけるのは避けた方がよいでしょう。
・かわいそうだね
・頑張ってね
・治るといいね
・そんなに落ち込まないでよ
・つらいのはあなただけじゃないんだから
・残り少ない人生だけど
・思っていたよりも元気だね
これらは、落ち込んでいる方にとってはつらい言葉です。もしかける言葉が見つからない場合は無理に発言しないで、そっとそばに付き添ってあげましょう。
やり残したことはないか聞く
好きなことや楽しくなれること、やりたいことはないか、ご本人に聞いてみましょう。自分のなかになにか目標となることがあると気持ちがポジティブに向かいやすくなります。
特になにかと制限が多い方は、いままでたくさんの我慢をしてきたはずです。「若いうちにやっておけばよかったな」ということもあるでしょう。行きたい場所や食べたいもの、やりたいことなど、ご本人の願望はないかたくさん聞いてあげてください。人生が楽しい思い出でいっぱいになるよう、家族でサポートしましょう。
とはいえ、ご本人は決して健康な状態ではないため、実際にすべてを実行できるかどうかは別問題です。そのときの体調や病状をみて、医師に判断を仰いだ上で決めましょう。
【余命宣告を受けたら】家族がやるべきこと

余命宣告を受けたあとに、家族がやるべきことについて確認しておきましょう。
治療方針を相談する
余命宣告後は、ご本人と医師、家族で今後の治療方針を決めなければいけません。その際に病気になった原因、今後の経過予測、治療方法などの説明を受けるかもしれませんが、すぐには理解できないケースもあるでしょう。その場合は、いますぐに治療方針を決めなくても大丈夫です。
ご本人と家族が納得する方法を選択することが最も大切なので、医師としっかり相談しながら決めましょう。相談した際に、もし不明点や疑問に思うことが出てきた場合は、決してそのままにせず早めに医師に相談して解決しましょう。
余命宣告時の治療方針の種類は主に3種類
余命宣告時の治療方針は主に3種類あり、1つ目は積極的な治療、2つ目は延命治療、3つ目は緩和ケアになります。以下ではそれぞれの特徴をご紹介します。
積極的な治療
病気の完治を目指す場合は、積極的に治療を受ける必要があります。たとえば、がんの場合の主な治療は放射線治療や投薬、手術などです。それらの治療は病院で受けなければいけないため、長い時間を病院で過ごすことになります。
治療が長引けば長引くほど、ご本人はもちろん家族の負担も大きくなり、お互いに心身共に疲弊してしまったり、金銭的に十分な余裕がない場合は医療費の工面に苦労したりするでしょう。
延命治療
寿命を延ばすための治療が延命治療です。延命治療でも場合によっては投薬や手術を行いますが、これは完治を目指すための治療ではありません。未来に目標がある方がその目標を達成するために延命治療を選択するケースが多くなっています。
たとえば、「子どもの結婚式に参列したい」「最期に旅行に行きたい」「やり残したことをやりたい」などの目標に向けて命を繋げるための治療になります。
緩和ケア
緩和ケアは、投薬などによる延命を目的としない治療方法です。容体が安定していれば、自宅で過ごす時間を持てたり、旅行に行ったり、家族との思い出づくりを楽しめます。
緩和ケアでは、医師や看護師、ソーシャルワーカー、心理士などの医療関係者がチームとなりケアを行いますが、病気の治療は止めることになります。不安や心配なことがある場合は、医師に質問してみましょう。
エンディングノートを準備する
エンディングノートを準備していない場合は、ぜひ準備に取り掛かってみてください。エンディングノートを準備し活用することで、残された家族にかかる負担は減ります。なによりも、ご本人にとって心の内を記すことで、死に対する準備が整っていくはずです。
相続・遺言書の準備
ご本人と家族が協力して、ご本人の財産状況を把握しておきましょう。ここで重要なことは、プラスの財産だけではなく借金などのマイナスな財産も含めて、包み隠さずすべてを明らかにすることです。
もし、相続に関してご本人の希望がある場合は遺言書を作成します。ご本人が亡くなったあとの親族同士の相続トラブルを防ぐため、遺言書を作成する場合は必ず弁護士や税理士などの専門家に相談しましょう。
生命保険の契約内容に関する確認
ご本人が生命保険に加入している場合は、保険会社に連絡をして余命宣告を受けた旨と現状を説明しましょう。そして、保険金の確認や手続きの段取り、特約の有無などを確認します。
リビングニーズ特約を付帯している場合は、ご本人が生きているうちに保険金を受け取ることが可能です。
葬儀に備える
あまり積極的に考えたくないことだと思いますが、あらかじめ葬儀の準備をしておくことも重要です。事前にある程度決めておくことで、いざ亡くなった際の精神的負担や肉体的負担を軽減できます。
また、葬儀では多くの費用が必要です。事前に準備をして金額を把握しておくことで、葬儀を予算内で済ませる計画を立てやすくなります。
【室蘭市視点のワンポイント】地域で頼れる先
在宅療養や介護、福祉サービスの情報は、市の窓口や地域包括支援センター、かかりつけ医に相談するとスムーズです。医療ソーシャルワーカーに、在宅医・訪問看護・訪問介護の連携や、各種制度(高額療養費・医療費助成など)の活用についても相談してみましょう。
まとめ:いちばん大切なのは「その人らしさ」を守ること
余命宣告は、残された時間をどう使うかを家族で考える合図でもあります。医学的な選択と同じくらい、語り合い・触れ合い・小さな楽しみを重ねることが、かけがえのない日々を形作ります。室蘭市でも、医療・介護・葬儀の専門家は伴走してくれます。ひとりで抱え込まず、周囲の手を借りながら準備を進めていきましょう。
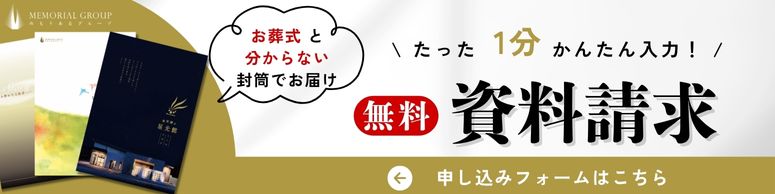




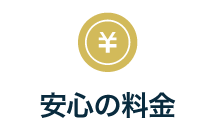
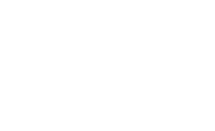
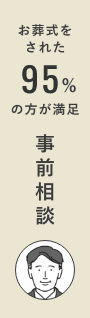


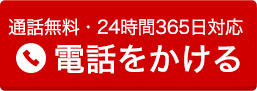
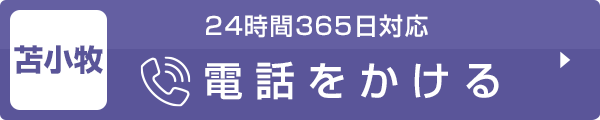
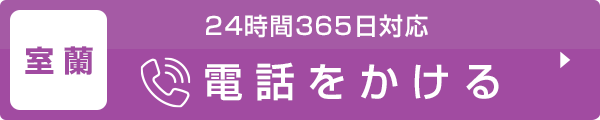
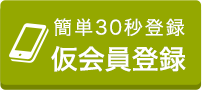
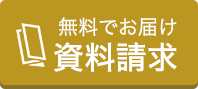

クチコミ件数
1,524件平均評価
4.9