葬儀の基礎知識
葬儀費用は誰が支払う?負担やトラブル回避のポイント
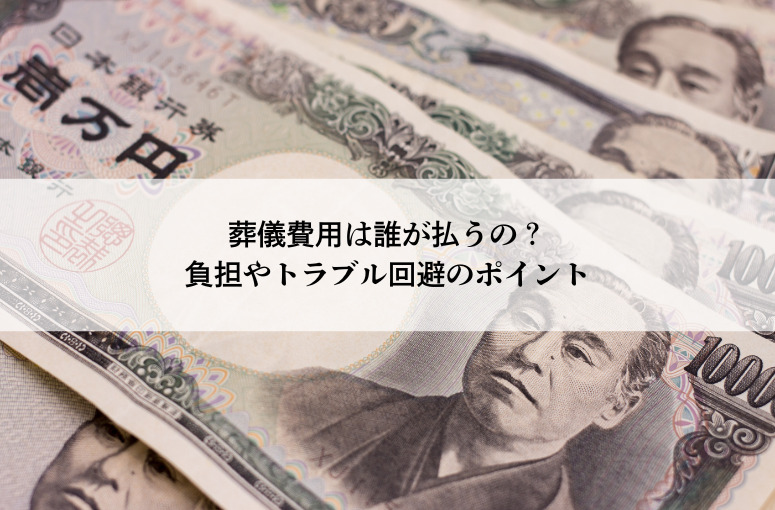
公開日: 2025年9月19日 9:00
最終更新日: 2025年10月30日 09:30
家族に不幸があった場合、「葬儀費用を誰が支払うのか」「どのくらいの負担になるのか」と心配になる方も多いことでしょう。葬儀費用の負担者について法律上の規定はありませんが、日本の慣習上、喪主が支払うケースがほとんどです。
とはいえ、葬儀費用の負担については家族構成あるいは家族関係、故人の遺言などを踏まえながら、親族間で十分に協議することが重要です。そこでの話し合いができていないと、後々のトラブルにつながるケースが多々あります。
今回の記事では、葬儀費用は誰が支払うべきなのかについてやトラブルに発展する具体的な例、トラブルを避ける方法などについて解説します。
「葬儀費用」とは何を指す?
葬儀費用とは、主に葬儀会社に支払う費用、香典返し、飲食代など参列者への接待費用、寺院や神社などに渡す謝礼などが含まれます。
基本的に葬儀費用は喪主が全額負担する
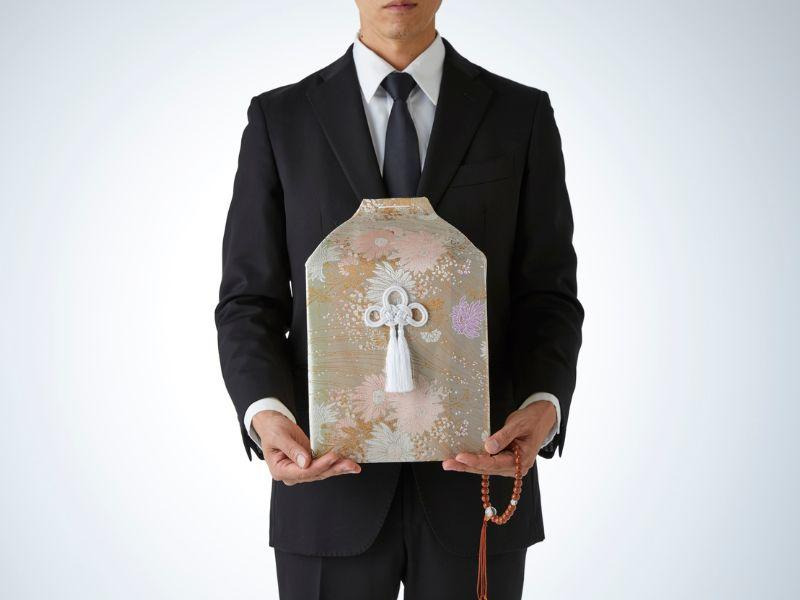
日本の慣習上、葬儀費用は葬儀の主催者である喪主が全額負担するケースがほとんどですが、これは法律上の決まりではありません。
本来であれば葬儀の取り仕切りを行う者=喪主、葬儀費用を負担する者=施主として役割が分かれていましたが、現在では多くの場合、喪主が葬儀費用も負担しているため、喪主と施主は兼任と考えて良いでしょう。
喪主を決める優先順位
基本的に、喪主は以下の優先順位で決められます。
- 配偶者
- 長男
- 次男以降の子ども(男性)
- 長女
- 次女以降の子ども(女性)
- 故人の両親
- 故人の兄弟
故人と共に暮らしていた家族(配偶者・故人の子ども(年齢順)・故人の両親など)が喪主を務めることが多く、次に故人の兄弟・姉妹の順になります。なお、故人の子どもが複数人いる場合は、男性が優先されることが多いです。
喪主以外で葬儀費用を負担するケース

喪主以外の人が葬儀費用を負担するケースもあります。
喪主1人で葬儀費用を負担できない場合は複数人で分割して負担し合います。また、喪主とは別に、施主が葬儀費用を負担するケースもあるので確認してみましょう。
複数人で葬儀費用を分割して負担する
故人に配偶者がいないため兄弟姉妹で葬儀費用を負担するケースや、配偶者が逝去しているため子どもたちで葬儀費用を負担するケースなどの場合は、喪主を含め複数名で葬儀費用を分割することがあります。その場合、全員が同じ負担割合になるパターンか、それぞれで負担割合が異なるパターンかに分かれます。
なお、故人の兄弟・姉妹間で葬儀費用を負担する場合であっても、末っ子が学生であったり、失業中あるいは無収入の状況であったりする場合は支払いが難しくなるでしょう。いずれにしても全員が納得のいく割合になるよう話し合うことが重要です。
施主が負担する
前述した通り、本来、葬儀費用の支払いを担うのは喪主ではなく施主です。近年では喪主が施主を兼任して葬儀費用を負担するケースが増えていますが、喪主とは本来、葬儀の契約や手続きを行う役割だけを担います。
ただし、喪主が葬儀費用を支払う能力がない場合は、施主が葬儀費用の負担を行うことがあります。
葬儀費用を誰が支払う?起こりうるトラブルの例

ここでは、葬儀費用の負担を巡って起こりうるトラブルについてご紹介します。
親族に支払いを拒否された
親族間で話し合った末、葬儀費用は喪主が一旦立て替えて支払い、後ほど親族全員で分割するということで同意していたが、実際に葬儀費用を請求すると支払いを拒否されたケースもあります。
喪主から支払いを請求された
喪主が葬儀費用を立て替えたものの、その分を後から親族に請求するケースがあります。たとえば、故人の長女(姉)が葬儀費用を立て替えたあとに、相続の話し合いのタイミングで長男(弟)に半分負担してほしいと請求するなどです。
払う人が決まらない
親族間の話し合いが難航し、なかなか費用の負担者が決まらないケースもあります。喪主が決まらなければ葬儀開催が難しくなるため、適切なタイミングで執り行うことができなくなります。
葬儀費用がきっかけで相続問題に発展する
相続財産から葬儀費用を控除することで、他の相続人への相続金額が減り、トラブルに発展するケースがあります。相続問題は長期化することで親族間の仲が悪化し、泥沼化してしまうことも多々あるので注意しなければいけません。
葬儀費用に関するトラブルを防ぐ方法

葬儀費用をめぐっては、さまざまな要因でトラブルに発展しがちです。また、お金に関する問題は長期化しやすく、親族間で大きな亀裂が入ってしまう可能性も。お金のトラブルを抱えないようにするには、あらかじめ葬儀費用の負担者を事前に決めておくことがポイントです。
ここでは、葬儀費用の負担者を事前に決める方法についてご紹介します。
①兄弟・姉妹、親族間で事前協議を行う
トラブルを避けるための最善策は、故人が亡くなる前に兄弟・姉妹、親族間で協議を行っておくことです。このときに話し合っておくべき項目は以下の通りです。
・葬儀費用の負担者と負担割合
・葬儀の規模・形式
・香典の受取人
・相続財産から払うかどうか
なお、上記以外にもトラブルの元になりそうな内容があれば、事前の協議のなかで話し合っておきましょう。
葬儀費用の負担者と負担割合
支払いの際に揉めないためには、事前の話し合いで葬儀費用の負担者と、負担する割合を決めておくことが重要です。なかには無職や学生で支払い能力がないケース、家計的に支払いが厳しいケースもあると思います。お互いの家計状況や現在の収入などを伝えながら、話し合いを進めていきましょう。
葬儀の規模・形式
葬儀の規模や形式によって、負担が変わってきます。どのような葬儀にするのかを事前に想定しておくと「考えていたより葬儀費用がかかってしまった」などの不測の事態を避けることが可能です。
葬儀の規模や形式を決める際は、以下の基準で選びましょう。
・故人の意向
・葬儀にかかる費用
・葬儀に呼ぶ人数
上記の基準を定めたら、葬儀形式を選びましょう。
・一般葬(30人~) :約200万円~
・家族葬(10人前後):約40~150万円
・一日葬(10人~) :約30~50万円
・直葬(10人前後) :約10~40万円
なかには、喪主の意向で盛大に葬儀を行ったものの予想以上に費用が高くついてしまい、後から葬儀費用の負担を親族にお願いする、といったケースもあります。そのようなトラブルにならないためにも、事前に葬儀の規模や形式を決めておくことは重要です。
香典の受取人
香典は、本来喪主が受取人となりますが、これには法律的な根拠はありません。「香典を受け取るのは喪主」という考え方は、古くからの日本の慣習として一般的になっているに過ぎないのです。そのため、葬儀費用を払った後の香典の余剰分をめぐるトラブルに発展するパターンもあります。
葬儀を仕切ったり業者を手配したりなど、喪主にはさまざまな労力がかかることから、余剰分に関しては喪主が受け取るケースがほとんどですが、別の人が香典の受取人として名乗りをあげることもあります。
香典の受取人は、葬儀費用の負担額、葬儀手配者の時間的負担・労力を加味して、双方が納得できるかたちで決めましょう。
相続財産から払うかどうか
本来、葬儀費用は相続人が支払わなければならない債務ではなく、相続の対象ではありません。しかし、実際には故人の死後には葬儀を行わなければならず、必ず葬儀費用が発生するため、日本では相続財産から葬儀費用を控除することが認められています。
ただし、相続財産から葬儀費用を控除することで、相続人同士で受け取れる金額が減ってしまうため、そのことをよく思わない方がいるかもしれません。相続財産から葬儀費用を算出する場合には、相続人同士の事前協議に加えて、生前の遺言書作成が有効です。遺言書については後述します。
②生前のうちに遺言書を作成してもらう
遺言書を生前に作成しておいてもらうと、後々になってトラブルに発展する可能性が下がります。ただし、効力が発生する遺言事項は法律で定められおり、死後に発生する葬儀費用に関しては法律的効力は認められていません。
それでも、葬儀費用の負担について故人の意向が記載されている場合は、遺族側が故人の遺志を汲み取り、遺言書の内容に合意するパターンが多くなるでしょう。
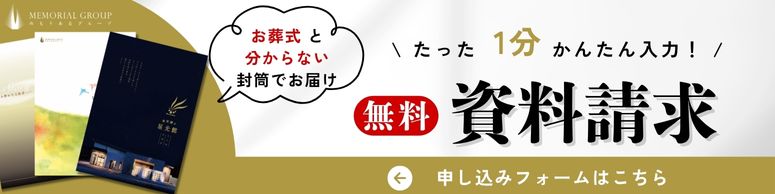




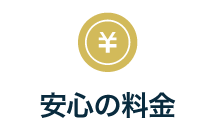
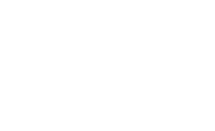
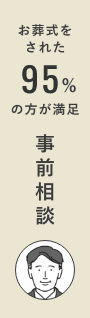


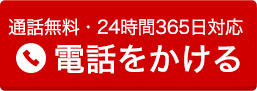
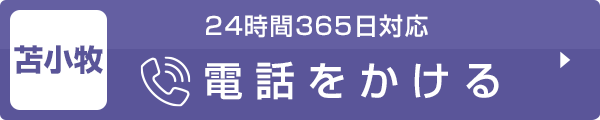
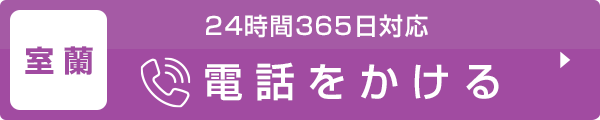
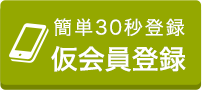
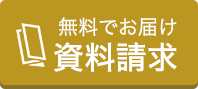

クチコミ件数
1,524件平均評価
4.9