葬儀の基礎知識
【苫小牧市】親が亡くなった後に必要な手続き|2年・3年・5年以内のチェックリスト
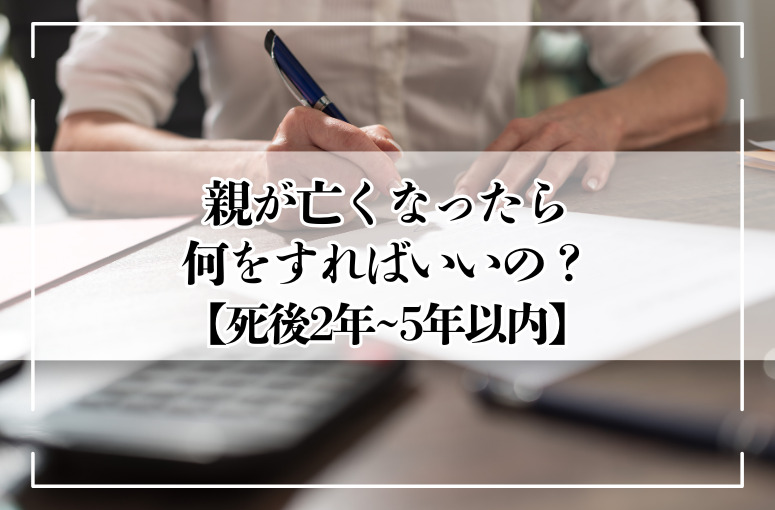
公開日: 2025年7月4日 9:00
最終更新日: 2025年10月28日 09:30
身内の死に直面すると、何から手を付ければよいか分からなくなりがちです。とくに親が亡くなった場合は手続きの数も多く、期限が決められているものもあります。本記事では苫小牧市での手続きを中心に、必要な流れを「2年以内・3年以内・5年以内」に分けて整理しました。
▼関連記事
① 親が亡くなったら何をすればいいの?【死後当日~7日目】
② 親が亡くなったら何をすればいいの?【死後14日目~10ヶ月】
目次
【2年以内】申請期限に注意したい3つ
① 国民年金の「死亡一時金」請求
第1号被保険者として36ヶ月以上保険料を納め、老齢・障害基礎年金を受給せずに亡くなった場合、死亡一時金を請求できます(請求はご遺族)。受給順位は〈配偶者→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹〉の順です。手続きは苫小牧市役所または年金事務所・年金相談センターで行います。
受給額の目安:納付月数に応じておおむね12〜32万円。付加保険料を36ヶ月以上納付していた場合は+8,500円。
※遺族基礎年金を受け取る場合は死亡一時金は支給されません/寡婦年金と併給不可(いずれか選択)。
② 葬祭費・埋葬料の給付金
葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療):葬儀主宰者に支給。苫小牧市の葬祭費は3万円(室蘭市も同額)。
埋葬料(健康保険):社会保険加入者が亡くなった場合に一律5万円。健康保険組合によっては付加給付あり。
申請先:葬祭費は苫小牧市役所、埋葬料は勤務先の健康保険組合(もしくは協会けんぽ)。
③ 高額療養費の支給申請
入院・治療で自己負担が上限額を超えた分が払い戻されます。亡くなった後でも未支給分は相続人が請求可能。申請先は、国保・後期は苫小牧市役所、社保は加入していた健康保険組合です。
自己負担限度額の目安:住民税非課税世帯で約3万円、一般所得層で約5〜8万円が多いケース。
【3年以内】生命保険(死亡保険金)の請求
生命保険に加入していた場合、受取人は死亡から3年以内に保険金を請求します。金額や契約内容によっては相続税・所得税・贈与税の対象となる場合があるため、早めに確認・申告しましょう。
【5年以内】年金関連で忘れやすい3つ

① 未支給年金の請求
支給日前に亡くなった分の年金(原則、前月・前々月分)は、生計を同じくしていた3親等内の親族が請求可能。
※未支給年金は相続財産ではなく請求者の固有財産のため、遺産分割の対象外。相続放棄後でも請求できます。
② 遺族年金の請求(遺族基礎・遺族厚生)
生計維持関係(同居・仕送り・扶養など)と所得条件を満たせば、子のある配偶者や子、配偶者、父母、孫、祖父母が対象。受給額は制度区分・加入状況・報酬比例額などで異なります。
③ 寡婦年金の請求
夫が国民年金第1号被保険者で、遺族基礎年金を受けられない妻が対象。一定の要件を満たすと、60〜65歳の間、夫の老齢基礎年金見込み額の4分の3を受給できます。請求は苫小牧市役所または年金事務所へ。
期限はないが早めに済ませたいこと
運転免許証・パスポート・マイナンバーカードの返却/固定資産税・住民税の請求先変更/電気・ガス・水道・電話・NHKの名義変更・解約/クレジットカード解約/ネット・SNSアカウントの削除 など。放置すると請求や二重課金の原因に。
苫小牧市でのお葬式や各種手続きのご相談は、地域密着の「めもりあるグループ」へ。実務と心の両面を丁寧にサポートします。
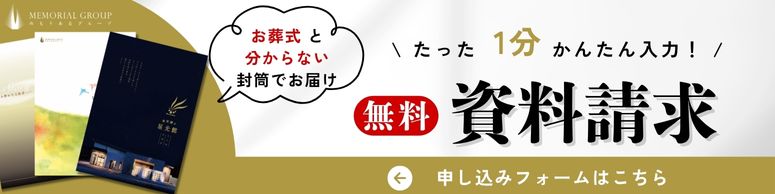




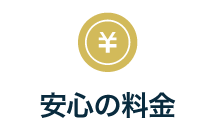
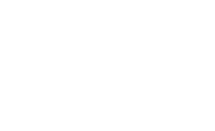
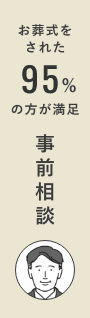


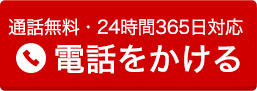
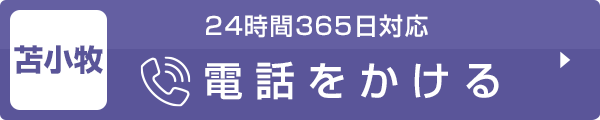
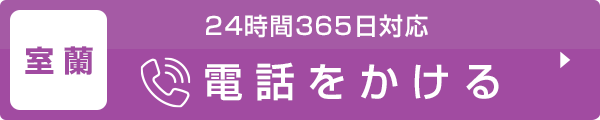
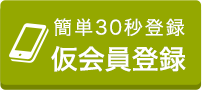
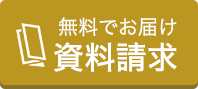

クチコミ件数
952件平均評価
4.9