葬儀の基礎知識
「志」と「寸志」の違いについて

香典返しの表書きで見かける「志」という言葉。似たような言葉で「寸志」もありますが、みなさんはこれらの使い分け方をご存知でしょうか。もし知らないまま間違って使ってしまうと、相手の方に対して大変失礼になることもあるので注意が必要です。
今回は、志と寸志の違いや意味、使い方、相場、渡す際の注意点を解説します。
目次
「寸志」と「志」の違い
「志」と「寸志」は似ている言葉ですが、香典返しに「寸志」は使いません。
寸志は、目上の人が目下の人に対して渡すお礼などの金品、差し入れを指す言葉であるために、間違えて使うと大変失礼にあたります。表書きを書く際には特に注意しましょう。
「志」とは
ここでは「志」の意味や、表書きに「志」を使う理由などについて解説します。
「志」という言葉が持つ意味
「志」という言葉には「心に決めたこと」や「目標」、「思いやりの気持ち」という意味があります。特にご葬儀においては「お礼を込めたお返しの気持ち」という意味で、のし紙の表書きに使われています。
「志」を使うようになった由来
一般的には弔事に使われることが多い「志」という言葉。実は、弔事で「志」が弔事で使われるようになった明確な由来は不明とされていますが、「志」という言葉には心の動きや、その人の気持ちが含まれているため、それが転じて相手への感謝の気持ちを表す言葉として弔事で使われるようになったと考えられます。
のし紙の表書きに「志」を使う理由
日本では古くから、贈り物に目録などの名目をつける慣習がありました。のし紙の上部に記載される表書きは、それを簡略化させたものです。
弔事の際の贈り物の表書きを「志」とする理由は、宗派を問わずに使えるからだといわれています。仏式の場合、地域によっては「満中陰志」や「忌明」、神式の場合は「偲び草」、キリスト教の場合は「記念品」と表書きされることもあります。
心づけを渡す場合も「志」を使う
葬儀に携わってくれたスタッフや、車の運転手などに渡すお金のことを「心づけ」といいます。葬儀を執り行ってくれたことに対する感謝の気持ちを表すため、心づけの表書きには「志」と書きます。
法事のお返しも「志」を使う
法事については、地域によっては何回忌なのかで水引の色を使い分けることもありますが、表書きには「志」を記載して問題ありません。また、志以外に「粗供養」を用いることもあります。
「寸志」とは
ここでは、寸志の意味や相場について解説します。
「寸志」という言葉が持つ意味
「寸志」という言葉には「ほんの少し」という意味が含まれており、「お礼や感謝の気持ちを込めたささやかな贈り物です」という謙遜する思いが込められています。一般的には、目上の方から目下の方への贈り物の際に用いられています。
寸志を渡す具体的なシーン
【ビジネスシーン】
・上司が部下へのお礼として渡す
・上司が幹事へのお礼として渡す
【プライベート】
・結婚式の手伝いをしてくれたスタッフへのお礼として渡す
・弔事において喪主が配膳スタッフへのお礼として渡す
・僧侶へのお礼として渡す
また、僧侶に渡すお礼には「お布施」という言葉も使われます。よく「寸志」と「お布施」を混同しがちですが、「お布施」とは仏様への感謝の気持ちを表すものなので寸志とは区別して考えましょう。
寸志の相場
地域や慣習、関係性にもよりますが、「寸志」の相場は1,000~5,000円ほどになることが多いです。しかし、お手伝いの内容によっては数万円の寸志を渡すケースもあるため、事前に葬儀社に確認しておくとよいでしょう。なお、親族に渡す場合は高額になる傾向があります。
一方、近年では「寸志もすべて葬儀代金に含む」と明示する葬儀社が増えており、寸志を求めないケースも多くあるため、葬儀社に確認するのがベターです。
寸志の包み方
「寸志」の包みには、のしの付いていない不祝儀袋や白無地の封筒など、控えめなものを用います。表書きには「寸志」と書き、その下には自分の姓(もしくは姓名)を記しましょう。水引は、紅白または黒白の結び切り、もしくはあわじ結びを用いるのが一般的です。葬儀や法事などの厳粛な場では、失礼のないよう適切な包みを使用しましょう。
寸志を渡すタイミング
寸志を渡すタイミングは、葬儀後、法要後に直接手渡しするのが一般的です。しかし、近年は葬儀社を通して渡すケースも増えているため、迷った場合は葬儀社に確認しましょう。
なお、寸志を渡す際は先にお礼を述べたあと、「わずかばかりですが」や「心ばかりですが」など謙遜する気持ちを表す言葉を添えるとよいでしょう。
「志」と表書きする掛け紙の書き方
「志」の掛け紙は、黒白、黒銀、銀白の水引が印刷されているものが一般的で、関西地方や北陸地方では黄白の水引を印刷したものもあり、これらは弔事全般の贈答品に用いられます。なお、仏式の場合には蓮の絵が印刷されていることもあります。
水引の色や蓮の絵の有無については、地域や慣習によって違ったり、葬儀のみなのか、四十九日までなのか、によっても違ったりするため、葬儀社に確認しておきましょう。
掛け紙の書き方は、水引の結び目の上部に「志」と書き、水引の結び目の下側には喪主の姓(もしくは姓名)、もしくは「田中家」のように「姓+家」で記します。
水引とは
水引とは、弔事や慶事で渡す贈答品にかける飾り紐のことを指し、祝儀袋や不祝儀袋、贈答品の包み紙などに用いられています。
水引の結び方には以下の4種類があります。
・結び切り
・あわじ結び
・蝶結び
・梅結び
葬儀で主に用いられる水引は、結び切りとあわじ結びです。どちらも、「同じことが繰り返されませんように」という意味が込められており、簡単にほどけないようになっています。また、あわじ結びには「これからも末永いお付き合いを」という意味が込められています。
反対に、蝶結びは「同じ幸せが何度も起こりますように」という意味が込められているため、ほどいて、また結べる蝶結びの形になっています。蝶結びの水引きは、弔事には不適切なので気をつけましょう。
表書きの文字の色
表書きの文字の色は、慶事の場合は濃墨で書きますが、弔事の場合、四十九日までは薄墨で書くのが基本です。薄墨で書くのは、「故人を偲ぶ悲しみで墨を濃くすることができない」という気持ちを表すためとされています。
一方で関東の一部地域では、法事のお返しや引出物の場合も濃墨で書くこともあるため、事前に地域の慣習を確認しておきましょう。





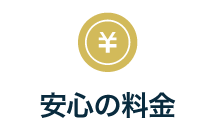
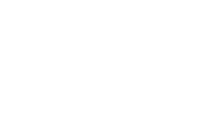
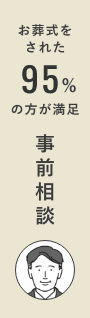


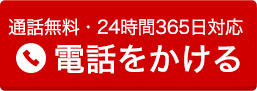
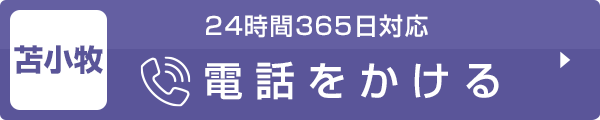
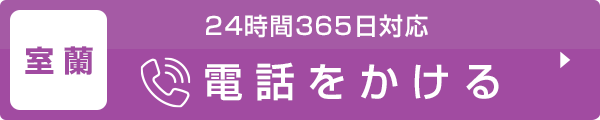
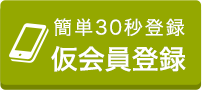
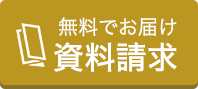

クチコミ件数
642件平均評価
4.94