葬儀の基礎知識
喪主挨拶で何を話す?例文・マナーと挨拶のポイント
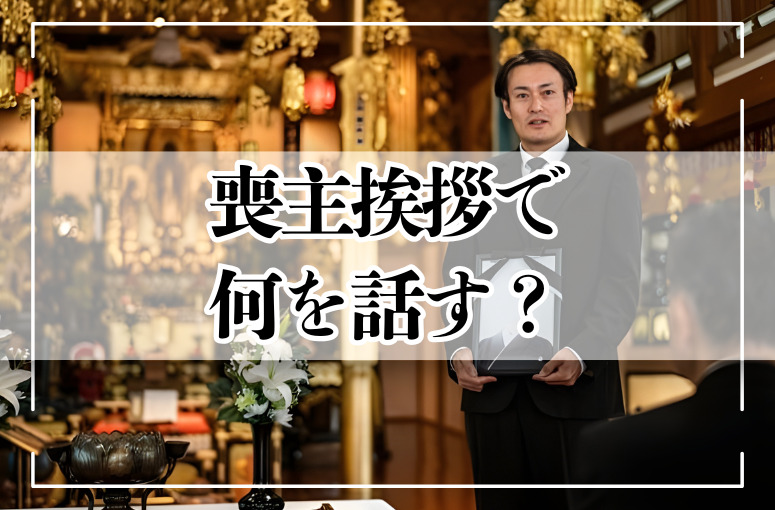
公開日: 2025年10月17日 09:00
最終更新日: 2025年10月30日 09:30
「喪主」とは、葬儀の運営や手続きを主立って行う人のことを指します。喪主にはさまざまな役割がありますが、そのなかでも「喪主挨拶」はとても大切な務めです。とはいえ、葬儀という慣れない場面で、喪主として適切な挨拶をすることは難しそうだと感じる方も多いでしょう。
今回の記事では、喪主挨拶が必要となるタイミングや一般的な喪主挨拶の例文、喪主挨拶のポイントについてご紹介しています。
喪主挨拶を行うタイミングは4か所
葬儀のなかで喪主が挨拶を行うタイミングは4か所あります。ここでは、そのタイミングや話す内容について解説します。
①通夜の最後
喪主挨拶が必要になる最初の場面は、通夜の最後(通夜振る舞いに移る直前)です。僧侶による読経、焼香、弔電のご紹介が終わった後に行われます。
このとき以下の構成で挨拶されることが一般的です。
1. 弔問していただいたことへのお礼
2. 故人が生前に受けた御恩へのお礼
3. 故人とのエピソード
4. 今後の力添えのお願い
5. 通夜振る舞いの案内
ただし、人前で挨拶するのが苦手な方の場合や簡単な挨拶で済ませたい場合、②は省略しても問題ありません。なお、「5. 通夜振る舞いの案内」に関しては、葬儀会社のスタッフから案内されることも多いため、喪主挨拶のなかでは不必要となる可能性もあります。
②通夜振る舞いの前後
通夜振る舞いでの喪主挨拶は2度あり、1度目は通夜振る舞い開始前、2度目は通夜振る舞い終了時になります。喪主挨拶の押さえるポイントは以下の通りです。
<通夜振る舞い開始前>
1. 参列いただいたことへのお礼
2. 粗宴ではあるがくつろいでほしいこと
<通夜振る舞い終了時>
1. お付き合いいただいたことへのお礼
2. 宴をお開きとすること
3. 明日の告別式の案内
なお、通夜振る舞いでの喪主挨拶では、故人に関するエピソードなどは必要ありません。どちらも簡潔に行いましょう。
③告別式
ほとんどの場合、通夜の翌日には告別式が行われます。この告別式の最後もしくは出棺時にも喪主挨拶が行われますが、このときに話す内容は通夜のときとほぼ同じです。
1. 弔問していただいたことへのお礼
2. 故人とのエピソード
3. 故人が生前に受けた御恩へのお礼
4. 今後の力添えのお願い
この喪主挨拶の後に出棺し、火葬場に行くことになります。
④精進落とし
本来、精進落としは四十九日目に行うものでしたが、近年では火葬の後に繰り上げて初七日法要を行い、その後、精進落としの席に進むことが一般的となっています。このときも通夜振る舞いと同様、精進落とし開始前と精進落とし終了時に喪主挨拶が必要です。
<精進落とし開始前>
1. 告別式を終えられたことへのお礼
2. 粗宴ではあるがくつろいでほしいこと
<精進落とし終了時>
1. お付き合いいただいたことへのお礼
2. 宴をお開きとすること
3. 今後も変わらぬお付き合いをお願い
4. 最後のお礼
精進落としが終わればそのまま解散となるため、「5. 最後のお礼」はいわば葬儀全体の締めの言葉になります。なお、四十九日法要などの日付がすでに決まっている場合は、併せてここで案内をします。
喪主挨拶の例文

ここでは「喪主挨拶の例文をご紹介します。
<例文>通夜での喪主挨拶
「妻」・「夫」の立場での喪主挨拶の例文をご紹介します。
故人の妻が喪主の場合
(弔問していただいたことへのお礼)
本日はお忙しいなか、夫○○の通夜にご弔問いただき、心より感謝申し上げます。
(故人が生前に受けた御恩へのお礼)
また生前賜りました数々のご厚情に、夫になり代わり深く御礼申し上げます。
(故人とのエピソード)
結婚から三十年が経ち、子どもたちもやっと手を離れ、これからは二人の時間を楽しもうと話していた矢先の出来事に、何も手につかない程のショックを受けました。
しかし、これからは夫の想いを私が紡いでゆき、家族で力を合わせて生きて参らねばと思うばかりでございます。
(今後の力添えのお願い)
皆さま方には、今後とも変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。
(通夜振る舞いの案内)
この後、ささやかではありますが酒宴の席を設けておりますので、お時間の許す方はぜひおくつろぎください。明日の葬儀・告別式に関しては、午前(午後)○○時より〇〇〇(会場名)にて執り行います。ご多用中恐縮ではございますが、ご参列賜りますようお願い申し上げます。本日はありがとうございました。
故人の夫が喪主の場合
(弔問していただいたことへのお礼)
本日はお忙しいなか、亡き妻のためにご会葬いただきありがとうございます。おかげをもちまして、葬儀も滞りなく終えることができました。
(故人が生前に受けた御恩へのお礼)
皆さまには生前よりお世話いただきましたこと、妻に代わり厚く御礼申し上げます。
(故人とのエピソード)
健康には人一倍気を遣っていた妻が病に倒れたときには、嘆き悲しむ日々と過ごしましたが、療養中であるにも関わらず私を励ます妻の強さや覚悟に触れ、私自身もしっかりせねばと少しずつ前を向くようになりました。
(今後の力添えのお願い)
これからは子どもたちと暮らしていくつもりでございますが、何かと不行届きも多いことと思います。 どうか、これからも変わらぬお付き合いをいただきますようお願い申し上げます。
(通夜振る舞いの案内)
この後、ささやかではありますが酒宴の席を設けておりますので、お時間の許す方はぜひおくつろぎください。明日の葬儀・告別式に関しては、午前(午後)○○時より〇〇〇(会場名)にて執り行います。ご多用中恐縮ではございますが、ご参列賜りますようお願い申し上げます。本日はありがとうございました。
<例文>通夜振る舞いでの喪主挨拶
通夜振る舞い開始前と終了時の喪主挨拶の例文をご紹介します。
通夜振る舞い開始前
(参列いただいたことへのお礼)
本日はお忙しいなか、夫○○の通夜にご弔問いただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
(粗宴ではあるがくつろいでほしいこと)
ささやかではございますが粗食をご用意いたしましたので、ごゆっくりおくつろぎくださいますよう、お願いいたします。
通夜振る舞い終了時
(お付き合いいただいたことへのお礼)
皆さま、本日はありがとうございました。今までの故人の軌跡となるお話をたくさん聞くことができ、大変うれしい気持ちでいっぱいです。
(宴をお開きとすること)
皆さまの思い出話をもっとお聞きしたいところではありますが、夜も更けて参りましたため、勝手ではございますがここでお開きとさせていただきます。
(明日の告別式の案内)
明日の葬儀は、〇〇〇(会場)にて、〇〇時より執り行います。何卒よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。
<例文>告別式での喪主挨拶
「妻」・「夫」の立場での喪主挨拶の例文をご紹介します。
故人の妻が喪主の場合
(弔問していただいたことへのお礼)
本日は故○○○○の葬儀に際し、ご多忙中のところご会葬くださりありがとうございました。
(故人が生前に受けた御恩へのお礼)
生前、皆さまからのひとかたならぬご厚誼を賜りましたことと併せて、心から御礼申し上げます。
(故人とのエピソード)
〇〇は、とにかく思いやりがある夫で、結婚から三十年が経ちましたが、結婚当初と変わらず私や子どもたちを気遣い、大切にしてくれる人でした。これからは夫の想いを私が紡いでゆき、家族で力を合わせて生きて参らねばと思うばかりでございます。
(今後の力添えのお願い)
皆さま方には、今後とも変わらぬご支援とご協力をお願い申し上げます。本日は最後までお見送りいただきましてありがとうございました。
故人の夫が喪主の場合
(弔問していただいたことへのお礼)
本日は故○○○○の葬儀に際し、ご多忙中のところご会葬くださりありがとうございました。
(故人とのエピソード)
2年前に癌が見つかり、お医者さまには「余命1年」と宣告されておりました。それからは家族全員で懸命に闘ってまいりましたので、夫としても悔いのない最期を迎えられたのではないかと考えております。
(故人が生前に受けた御恩へのお礼)
これまでにいただいた皆さまの温かいお言葉が、夫はもちろん私たち家族にとってもどれだけ励みになったか知れません。ここにあらためて御礼申し上げます。ありがとうございました。
(今後の力添えのお願い)
これからは家族3人で頑張って生きてまいります。どうか、今後とも主人の生前と変わらぬお付き合いをお願い申し上げます。本日は最後までお見送りいただきましてありがとうございました。
<例文>精進落としでの喪主挨拶
精進落とし開始前と終了時の喪主挨拶の例文をご紹介します。
精進落とし開始前
(告別式を終えられたことへのお礼)
本日はお忙しいなか、夫○○のためにご参列いただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございます。
(粗宴ではあるがくつろいでほしいこと)
ささやかではございますが粗食をご用意いたしましたので、ごゆっくりおくつろぎくださいますよう、お願いいたします。
精進落とし終了時
(お付き合いいただいたことへのお礼)
本日は、〇〇のためにお付き合いいただき、誠にありがとうございました。
(宴をお開きとすること)
このまま思い出話などをお聞かせいただきたいところではございますが、 皆さまもお疲れのことと思いますので、ここでお開きとさせていただきたく存じます。
(最後のお礼)
これからも故人同様、変わらぬお付き合いをいただきますようお願いいたします。本日は長い時間お付き合いいただきまして誠にありがとうございました。
喪主挨拶のポイント・マナー
喪主挨拶を行う際には、避けるべきポイント・マナーがあります。ここでは、喪主挨拶のポイント・マナーを見ていきましょう。
忌み言葉を避ける
慶弔の挨拶に適さない言葉は「忌み言葉」と呼ばれ、避けるようにしなければいけません。葬儀での主な忌み言葉は次のようなものが挙げられます。
重ね言葉
・ますます
・重ね重ね
これらは不幸が重なることを連想させるため、避けなければいけません。
ネガティブな連想をさせる言葉
・死
・苦
・数字の4と9
・生きていたころ
・枯れる
・終わる
・絶える
・消える
「死=永眠、逝去、他界」、「急死=急逝、突然のこと」、「生きていたころ=生前、元気だったころ」などに言い換えましょう。
長時間話さない
喪主挨拶は長くとも3分以内にとどめましょう。
簡潔にすると寂しく感じる方もいるかもしれませんが、気負った挨拶は特に聞き手にとって長く感じられるものです。印象的なエピソードを1個か2個に絞る程度にしましょう。
メモを見て話してもOK
喪主は挨拶以外にもやらなければいけないことが多くあります。慌ただしいなかでの喪主挨拶となるため、手元でメモを見ながら挨拶をしても失礼にはあたらないので安心して下さい。
無理に暗記するよりも落ち着いて話すことが重要です。特に、場所や時間などの連絡事項は明確に伝えましょう。
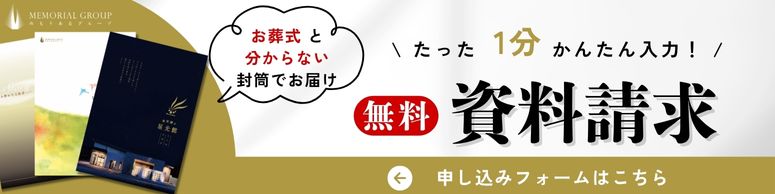




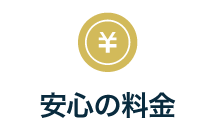
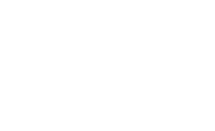
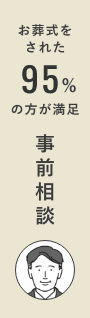


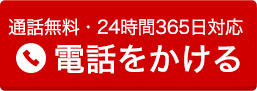
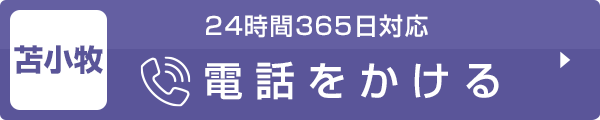
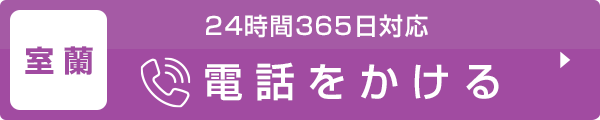
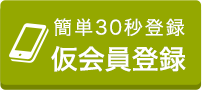
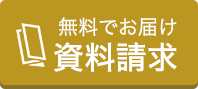

クチコミ件数
952件平均評価
4.9