葬儀の基礎知識
初七日法要の流れと準備ガイド!数え方と当日形式を解説
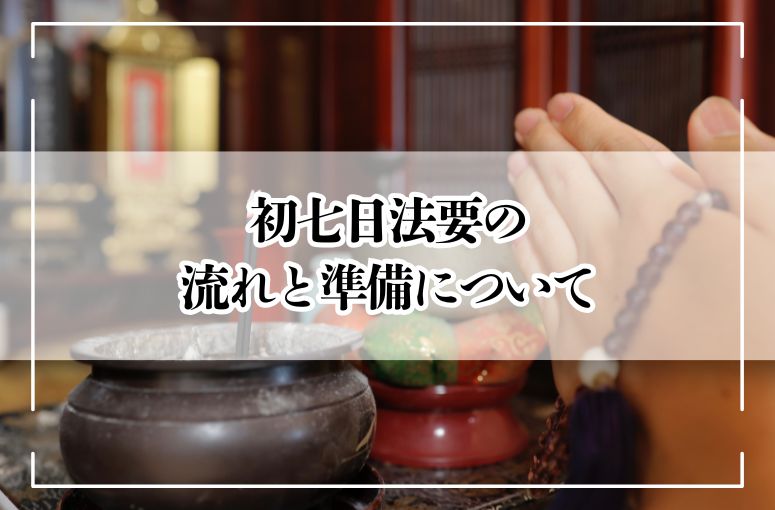
公開日: 2025年11月7日 9:00
最終更新日: 2025年11月7日 09:00
故人が亡くなってから7日目に行う初七日法要。「初七日法要」という言葉は耳にしたことがあるものの、それが何のために行われる法要なのか、法要ではどのようなことが行われるのかなど、詳しい内容はわからないという方も多いことでしょう。
今回の記事では、初七日法要を行う意味や法要の流れ、初七日法要までに行うべきことをご紹介します。
【解説】初七日法要について
まずは、初七日法要がどのようなものなのかについてご説明します。

初七日の数え方
一般的な計算方法は、命日を1日目と起算して、そこから7日目が「初七日」になります。ただし、関西などの一部地域では命日の前日を1日目として数える慣習があり、その場合は命日から6日目が「初七日」にあたります。
初七日はどういう日?
故人が三途の川(さんずのかわ)に到着するのは、亡くなってから7日目(初七日)だと言われています。三途の川を渡る前に生前の行いに対する審判を受け、裁きの結果によって激流、急流、橋のいずれかの三途の川の渡り方が決まるのです。
故人が緩やかな川を無事に渡れるよう、初七日法要では住職が読経を読み、遺族や親族、参列者は祈りを込めてお焼香をします。
四十九日まで七日毎に法要がある
故人は7日ごとに審判を受けなければいけません。6度の審判を受け、7度目となる四十九日目の最終審判で極楽浄土(ごくらくじょうど)に行けるどうかが決定します。四十九日までに行われる法要は以下の通りです。
<四十九日までの法要の名称>
・初七日(しょなのか):命日から7日目
・二七日(ふたなのか):命日から14日目
・三七日(みなのか) :命日から21日目
・四七日(よなのか) :命日から28日目
・五七日(いつなのか):命日から35日目
・六七日(むなのか) :命日から42日目
・七七日(しちしちにち・四十九日):命日から49日目
神道やキリスト教の場合は

仏教では7の倍数にあたる日が重要な日と考えられていますが、神道では10の倍数にあたる日が重要な日とされています。そのため神道では、命日から10日ごとに霊祭(みたままつり)が行われ、神葬祭の翌日には翌日祭、その後、十日祭、二十日祭、三十日祭、四十日祭、五十日祭、百日祭、一年祭と続きます。十日祭は、仏教の初七日法要にあたる日です。この日は神主を自宅に招き、祝詞をあげてもらいます。その際には、神主へ祭祀料(初穂料または玉串料)をお渡しします。
一方、キリスト教のカトリックでは、亡くなった日から3日目、7日目、30日目に追悼式(あるいは追悼ミサとも言う)が行われ、プロテスタントでは亡くなった日から7日目、10日目、30日目に記念式(あるいは記念集会とも言う)が実施されます。
初七日までの過ごし方

初七日法要までの期間は、故人を偲び、冥福を祈るための大切な時間となります。この期間にさまざまな準備を進めることで、ご遺族の心の整理もついてくるでしょう。ここでは、初七日法要に向けて必要な準備をご紹介します。
故人の供養
初七日法要まで毎日お線香をあげ、故人の冥福を祈りましょう。故人のためにお祈りをすることで、自身の心も少しずつ整ってくるはずです。
また、初七日法要まで、派手な行動は慎み、静かにおだやかに過ごします。故人の冥福を祈り、静かに故人を偲ぶ過ごし方を心がけてください。かつては、初七日法要を終えるまでは毎日、精進料理を食べることが一般的でしたが、現代では普段通りでも問題ありません。ただし、派手な場所に外食に出かけたり、大勢で宴会したりすることは避けるべきでしょう。
神棚封じ
神棚封じとは、神道における儀式の一つです。日本では各家庭で神棚を設けているケースがありますが、その場合、ご家族が亡くなった後すぐに神棚封じを行います。
神棚封じでは、神棚に白い半紙を貼り付けて、神様に目隠しをします。これは、神道において死を「穢れ(けがれ)」と捉えることから、神様にその状態を見せないようにしている儀式です。忌明けとなる故人の死後50日目まで封じたままにします。
※神道では50日目に「五十日祭」の儀式を行い、これをもって忌明けとなります。
お供え物を準備する
仏壇には、仏教の教えに基づき、食事や花、水、お線香を供えます。地域や家庭の習慣にもよりますが、お供え物は季節のフルーツやおはぎなどが一般的です。また、初七日までお線香は常に焚き、故人のために手を合わせましょう。
喪服を用意する
初七日法要に参列する際は、準喪服を着用します。男性はブラックスーツ、女性はブラックのワンピースもしくはスーツが一般的な装いです。靴やベルト、バッグなどの小物は、男女ともに黒で統一しましょう。
男性は清潔な髪形、女性はナチュラルメイクを意識して、見た目が派手にならないようにします。また、喪服と一緒に数珠やお布施も忘れずに準備しましょう。
相続手続き
大事な方が亡くなってまだ心痛癒えぬ時期かと思います。相続などの法的手続きは早めに処理するに越したことはないものの、急がずに進めていけば問題ありません。ただし、死亡届の提出など〆切がある手続きに関しては、忘れないうちに早めに行いましょう。
遺品整理
遺品整理も相続手続きと同様、そこまで急ぐ必要はありませんが、早めに進めておくと形見分けがスムーズに行えるでしょう。とはいえ、まだ心の整理がついていない状態のときに遺品整理を行うのはつらいと思います。無理せず、法要の準備を優先してください。
初七日法要のための準備
初七日法要を行う場合は、なるべく早めに準備を始めましょう。ここでは必要な準備についてご紹介します。
仏壇を整理する
自宅で初七日法要を行う場合は、仏壇や仏具をきれいに清掃しましょう。仏壇の前で僧侶が座るための座布団や、読経後にお出しするお茶やお茶菓子の準備も行いましょう。
参列者への連絡と食事の準備
初七日法要に出席していただきたい親戚や友人、知人には早めに連絡を入れましょう。法要後は、参列者を招いて精進落としとなる食事の席を設けるのが一般的なので、そちらも併せて準備を行います。ただし、準備する食事は派手ではなく慎ましいメニューにするのが望ましいでしょう。
香典返しの準備
初七日の間に香典返しの準備も行いましょう。いただいた香典の金額を確認して、その金額の3分の1~半額程度の品物を用意します。なお、香典返しで渡す品物は消え物がよいと言われているため、洗剤やお茶、コーヒー、お菓子などが定番となっています。
初七日法要の流れ

ここでは初七日法要の流れについてご説明します。
正式な初七日法要は自宅で執り行う
正式な初七日法要は、自宅に住職を招きお経をあげてもらい、お焼香をする流れになります。その後、精進落としの会食を行います。
ただし、近年では、葬儀の日に一緒に初七日法要まで実施されることが多くなっています。ただし、これは地域の風習によるため、初七日法要を別日にするかどうかについては親族や住職などと相談してみましょう。
また、葬儀の同日に初七日法要を行う場合、2種類のパターンに分けられます。その2種類については以下でご紹介します。
火葬前に法要を行う「式中初七日法要」の流れ
式中初七日法要(繰り込み初七日法要とも呼ばれる)*の場合は、葬儀・告別式終了後にそのまま同じ会場で初七日法要を行い、その後に火葬という流れになります。そのため、火葬場へは同行しないご遺族や親族にも供養してもらえるメリットや、移動の負担が少なくなり拘束時間が短くなるメリットがあります。
式中初七日法要の具体的な流れは以下の通りです。
・葬儀・告別式
・初七日法要
・出棺
・火葬
・会食(精進落とし)
ただし、本来遺骨に対して行う読経を遺骨になる前に行わなければいけないため、場合によっては住職に断られる可能性もあるので確認が必要です。
火葬後に法要を行う「戻り初七日法要」の流れ
戻り初七日法要とは、葬儀・告別式後に火葬場に移動して火葬を実施し、また会場に戻って初七日法要を行うというものです。火葬後に遺骨となった状態で読経を行えるため本来の形式に沿ったものとなります。
戻り初七日法要の具体的な流れは以下の通りです。
・葬儀・告別式
・出棺
・火葬
・初七日法要
・会食(精進落とし)
戻り初七日法要は、火葬後に会場へ戻って法要を行うため、移動の手間や、全体的な拘束時間が長くなる傾向にある点を考慮する必要があります。
初七日法要が終わっても忌明けではない
初七日法要が終わった後も忌中は続きます。四十九日法要が終わるまではこれまでと同じように故人を偲んで喪に服しましょう。
こちらの記事もご参考になさってください。
喪に服すとは?
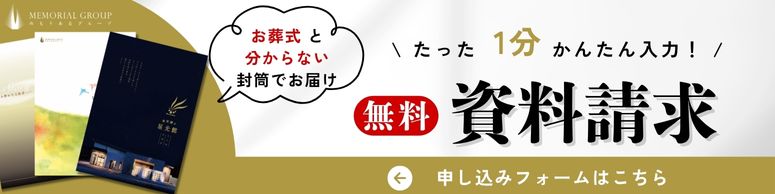




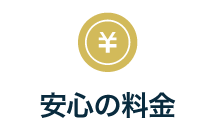
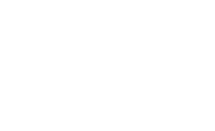
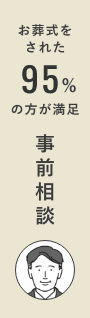


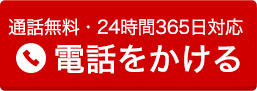
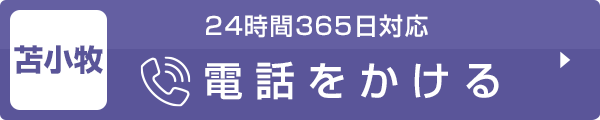
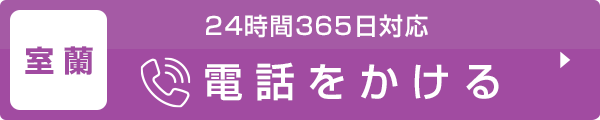
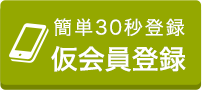
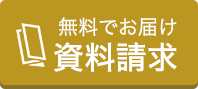

クチコミ件数
952件平均評価
4.9