葬儀の基礎知識
葬儀費用は相続税から控除できる!対象となる費用と注意点

葬儀は亡くなった方を極楽浄土まで送り届けるための大事な儀式ですが、費用が高額となることも多く、遺族にとっては経済的にも精神的にも大きな負担がかかります。
遺族の経済的な負担を和らげることができる制度として、相続税の債務控除があります。これは、遺族が負担した分の葬儀費用を相続財産から控除することができる制度です。これにより、数百万円以上かかる葬儀に関しては、相続税を大幅に引き下げることが可能になります。
ただし、控除できる葬儀費用には一定の基準があり、すべての葬儀費用を減額できるわけではありません。
今回の記事では、葬儀費用の控除対象になるもの・ならないものの詳細や注意点をご紹介します。
目次
葬儀費用について
最初に、葬儀費用について解説します。
葬儀費用は誰が支払う?
葬儀費用を誰が支払うかについての法的な決まりはありませんが、葬儀にかかる費用は喪主が支払うことが一般的です。
なかには、受け取った香典を支払いに充てたり、遺族で分担して費用を負担したり、相続財産を葬儀費用の支払いに充てたりするケースがありますが、いずれにしても相続人同士で話し合って決めることが重要です。
葬儀費用はどのくらいかかる?
葬儀費用とは、故人を弔うための儀式や埋葬のためにかかる費用のことを指します。葬儀は、仏式・神式・キリスト式・無宗教などの宗教によって分類されるため、葬儀にかかる費用はその宗教や葬儀の規模により異なります。
仏式での一般的な葬儀では、葬儀費用が200万円程度になることが多いとされていますが、近年では家族葬などの需要が増えており、小規模で簡素化した葬儀が望まれる傾向にあるため葬儀費用が低額で済むケースも多くなっています。
葬儀費用は相続財産から控除できる
葬儀費用は、必然的に生じる支出です。そのため相続税の計算をする際に、相続人が負担した葬儀費用を「葬儀費用」として相続財産から控除することが可能です。
ただし、葬儀にかかった費用をすべて控除できるわけではありません。税務上における葬儀費用とは、「葬儀や埋葬で発生する費用」に限定されています。これは国税庁の相続税法基本通達でその範囲を確認することが可能です。
ここでは相続税法基本通達に基づき、葬儀費用に該当するもの・該当しないものを解説します。
葬儀費用に該当するもの
相続税法基本通達では、以下のように定めています。
| 法第13条第1項の規定により葬儀費用として控除する金額は、次に掲げる金額の範囲内のものとする。(昭57直資2-177改正) (1) 葬式若しくは葬送に際し、又はこれらの前において、埋葬、火葬、納骨又は遺骸、若しくは遺骨の回送その他に要した費用(仮葬式と本葬式とを行うものにあっては、その両者の費用) (2) 葬式に際し、施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるものに要した費用 (3) (1)又は(2)に掲げるもののほか、葬式の前後に生じた出費で通常葬式に伴うものと認められるもの (4) 死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用 |
(引用:国税庁ホームページ 相続税法基本通達)
以下で、それぞれの具体的な例をご紹介します。
死亡診断書の発行費用
死亡診断書の発行費用は、葬儀費用として相続財産から控除ができます。死亡診断書は葬儀と直接的な関係はないように思いますが、火葬の許可を得るために必要な書類であるため控除の対象になります。
遺体や遺骨の運搬にかかった費用
遺体や遺骨の運搬にかかった費用も控除ができます。これも葬儀の費用ではありませんが、葬儀を行うために必要な費用であるため控除の対象です。
火葬や埋葬、納骨にかかった費用
火葬や埋葬にかかった費用も、葬儀費用として相続財産から控除することができます。また、納骨にかかった費用も控除可能ですが、納骨そのものにかかった費用に限定されるので注意が必要です。
なお、墓石の彫刻料、納骨式の際のお布施や食事代に関しては控除の対象外となります。
お寺や神社、教会へ支払ったお布施や戒名料、読経料
お寺や神社、教会へ支払ったお布施や戒名料、読経料も葬儀費用として控除ができます。これには、交通費として渡す「お車代」のほか「御膳料」も含まれます。
葬儀に係る飲食費用
通夜や告別式で必要となった飲食費用も葬儀費用として控除ができます。具体的には、通夜振る舞いや精進おとしなど、参列者をもてなすための料理や飲料代が対象です。
なお、飲食店・仕出し弁当のほかにも、スーパーやコンビニで購入したものも控除対象です。
葬儀のために葬儀会社に支払った費用
葬儀(通夜・告別式)のために葬儀会社に支払った費用については、相続財産から控除ができます。具体的には、祭壇設営費・葬祭場の使用料・棺・骨壺・霊柩車・マイクロバスなどの費用が含まれます。
葬儀を手伝ってもらった人への心づけ
葬儀の受付や食事の準備を手伝ってもらった人への心づけや、霊柩車の運転手への心づけも葬儀費用としてあげられます。
心づけは感謝の気持ちを示すために渡すものなので、一般的にはそこまで高額にはなりませんが、社会通念上相当と認められないような高額な場合は控除が認められないこともあります。
参列者に渡す会葬御礼費用
香典返しに加えて、参列者に対して会葬御礼の品を手渡す場合はその費用を控除できます。ただし、香典返しの代わりに会葬御礼の品を渡す場合、それは香典返しとみなされ、その費用は控除できません。※以下の章で説明しますが、香典返しは控除の対象外です。
葬儀費用に該当しないもの
相続税法基本通達では、以下のように定めています。
| 次に掲げるような費用は、葬儀費用として取り扱わないものとする。(昭和57直資2-177改正) (1) 香典返戻費用 (2) 墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料 (3) 法会に要する費用 (4) 医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用 |
(引用:国税庁ホームページ 相続税法基本通達)
以下で、それぞれの具体的な例をご紹介します。
特別処置で要した費用
ご遺体の解剖など、医学上もしくは裁判上必要となった特別処置にかかった費用は、葬儀費用にはなりません。ご遺体の解剖はすべての人に対して行われるものでないうえ、葬儀と直接関係がないからです。
しかし、前述した通り遺体の運搬に関しては葬儀費用として認められるため控除が可能です。
墓碑、墓地、位牌等の購入費用や墓地の借入料
墓地や墓碑、仏壇や位牌は、葬儀後に故人を供養するためのものであるため、葬儀において必要なものではありません。また、これらは相続税の非課税財産とされるため、これらにかかった購入費用や借入費用は控除の対象外です。
香典返しの費用
参列者から受け取る香典は非課税で、相続税や贈与税などの税金がかかりません。そのため、香典返しの費用は控除できる葬儀費用には該当しません。
初七日、四十九日、一周忌等の法要でかかる費用
初七日、四十九日、一周忌などの法要は、故人の供養のために執り行われる儀式であり、葬儀とは関係がないため、これらの費用は控除できません。
ただし、初七日法要を告別式と同じ日に行い、葬儀会社から内訳が区分されていない請求書が発行された場合は、葬儀費用に含めることも可能です。なお、石材店に支払った費用は葬儀費用には該当しないため、四十九日法要に合わせて行う納骨の費用は控除対象になる場合があります。
葬儀費用を控除するときの注意点
ここでは、相続財産から葬儀費用を控除する際の注意点をご紹介します。
領収書やレシートはすべて保管する
相続税の申告で葬儀費用を控除したい場合は、領収書やレシートを保管するのが鉄則です。
葬儀会社や料理店などに支払いをした際にもらった領収書や、スーパーやコンビニで買い出しをした際などにもらったレシートは、相続税の申告時まで紛失しないように大切に保管しましょう。
領収書がない場合はメモでもよい
僧侶に渡すお布施や心づけ、お車代に関して領収書をもらうことは難しいと思います。そのため、これらの費用については以下の内容をメモに記録することで領収書と同じ扱いにすることができ、控除が可能になります。
・支払先の名称もしくは氏名・住所
・支払った年月日
・支払った金額
・支払った明細(お布施代、心づけ代など)
不正は絶対にダメ
メモに記録するだけで葬儀費用を控除できるからといって、費用を水増ししたり架空の費用を申告したりすることは厳禁です。軽い気持ちで行うと、あとで必ず痛い目をみます。
税務署は絶対的な調査権限を持つため、調査が開始されると小さな不正もすぐに発覚します。もし不正が判明すると追徴課税や加算税も課されることになります。





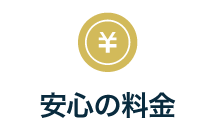
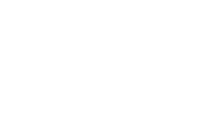
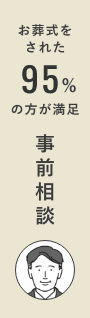


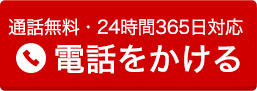
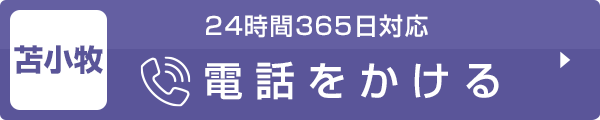
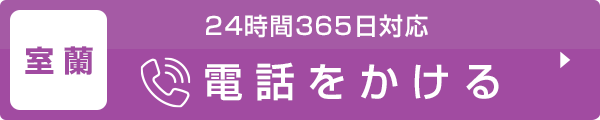
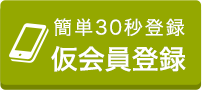
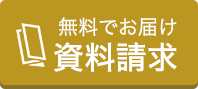

クチコミ件数
1,013件平均評価
4.88